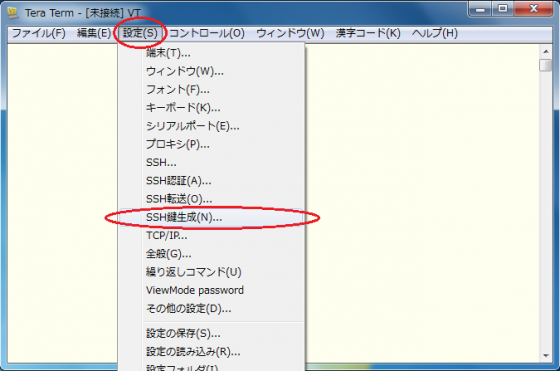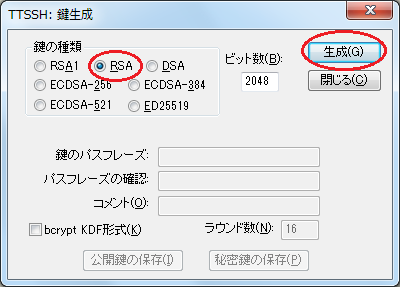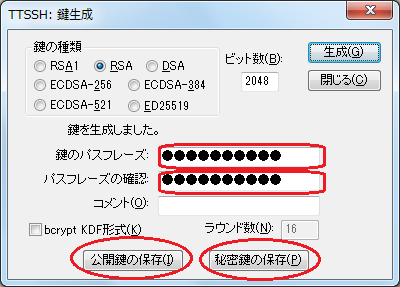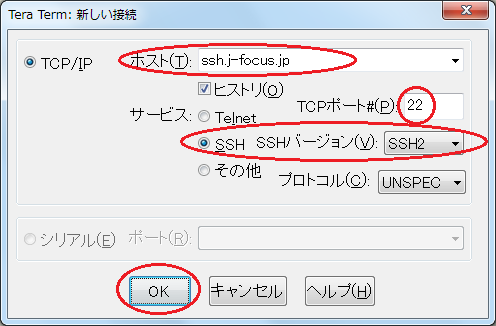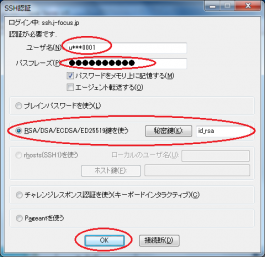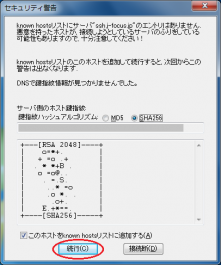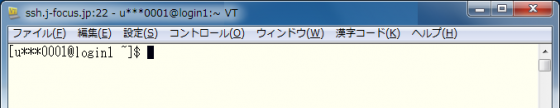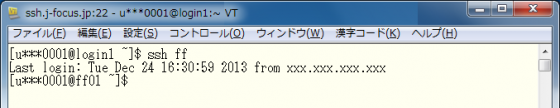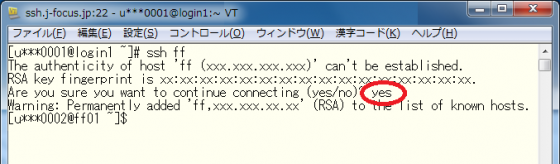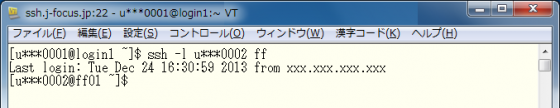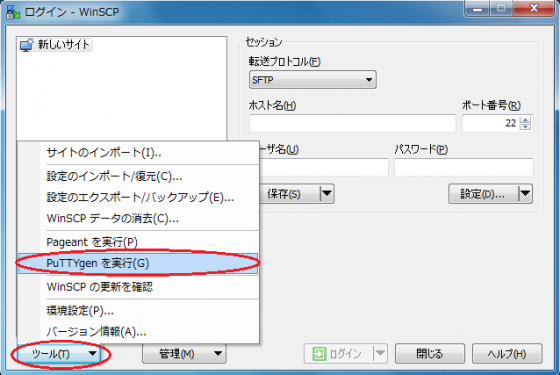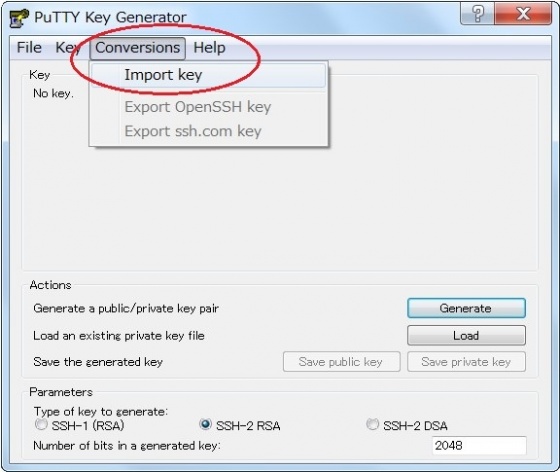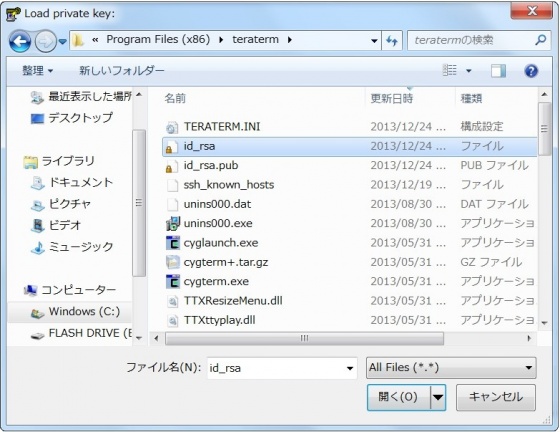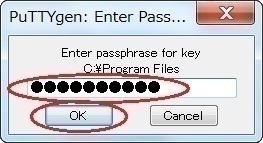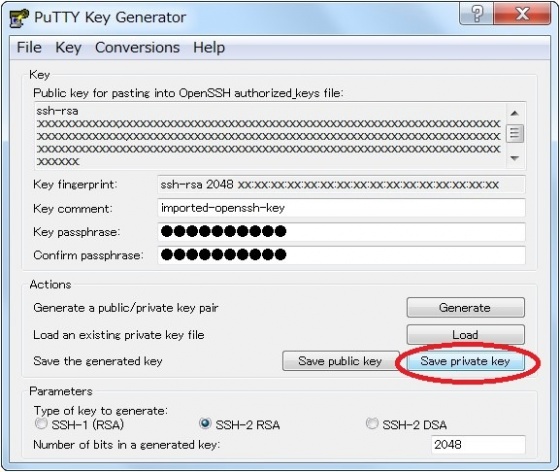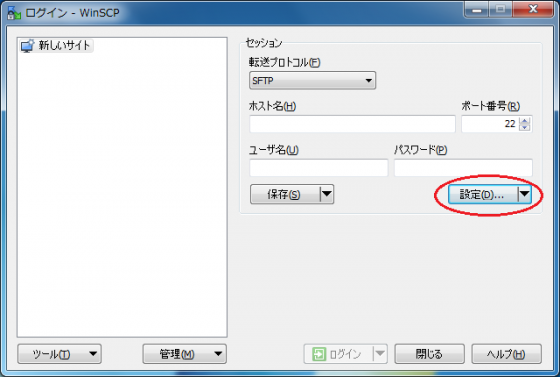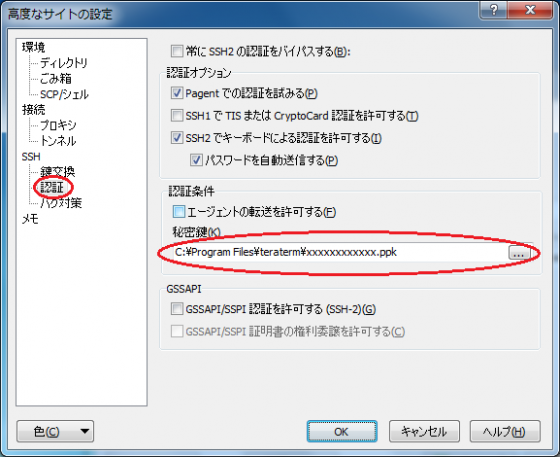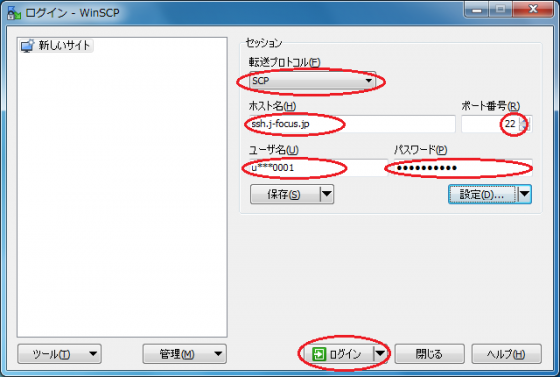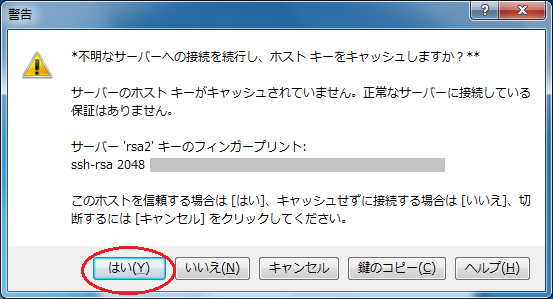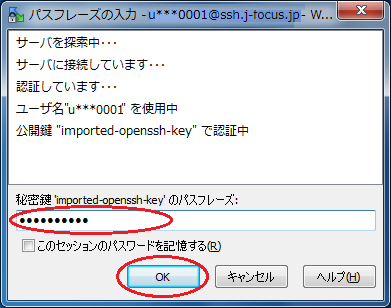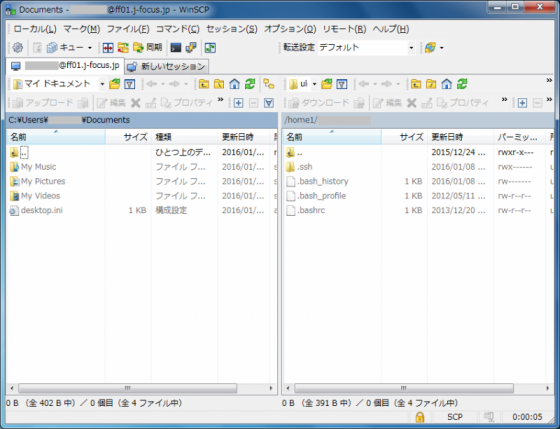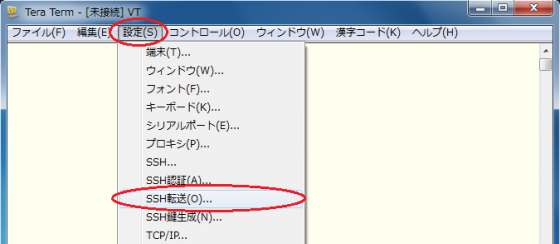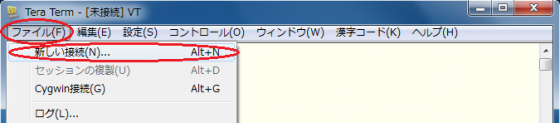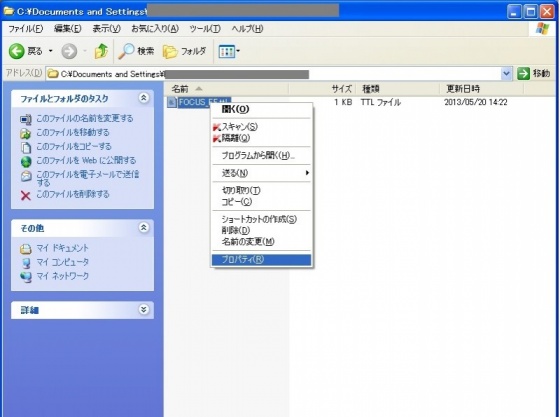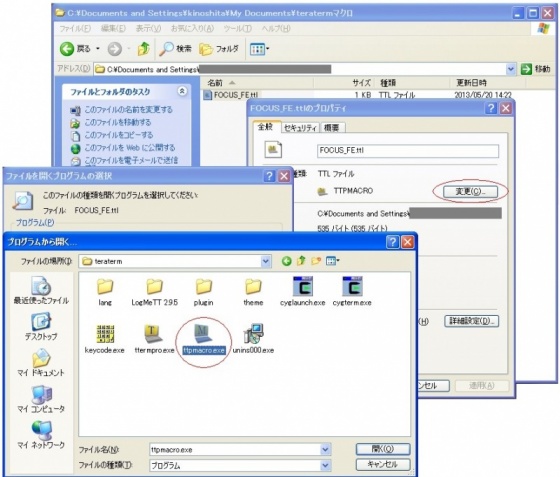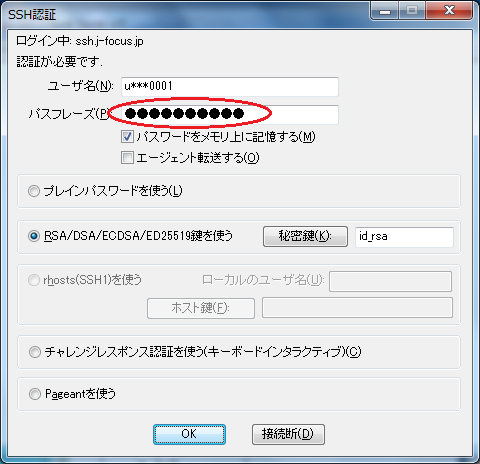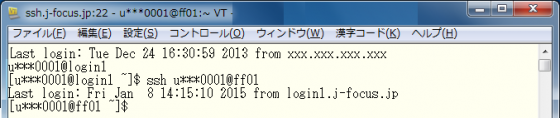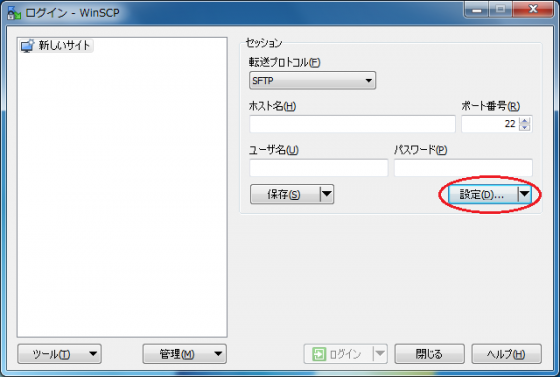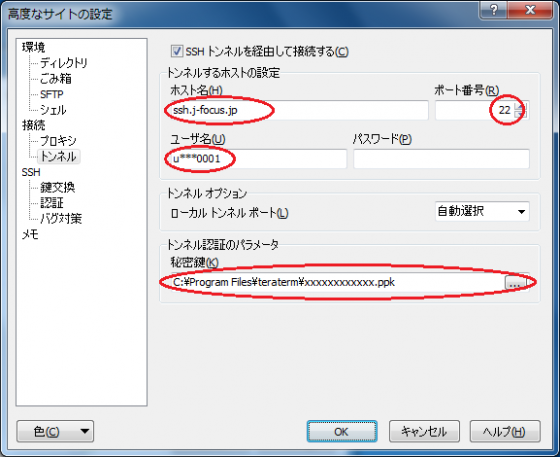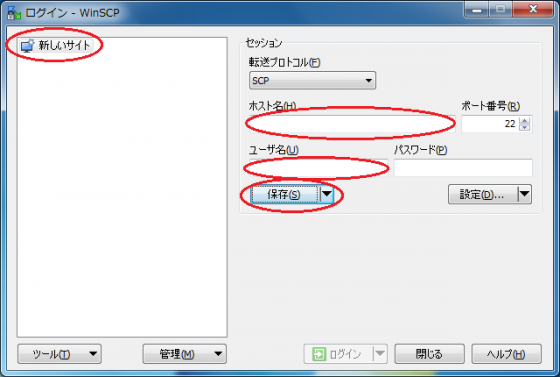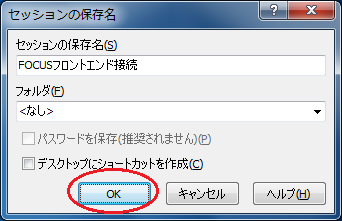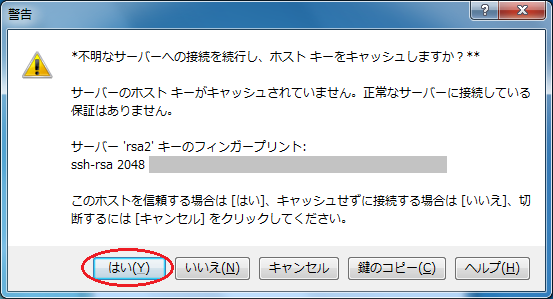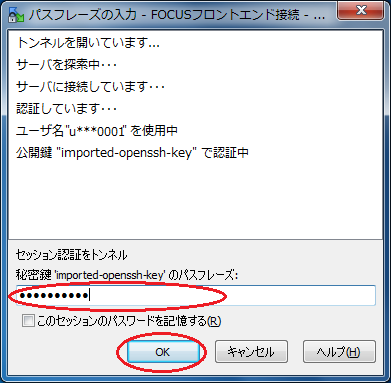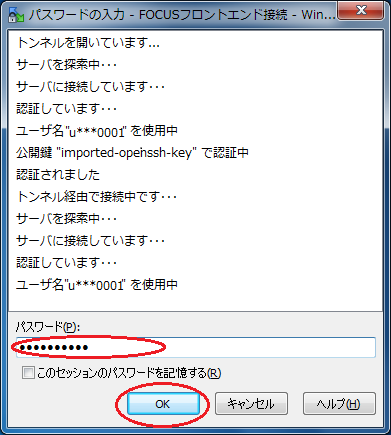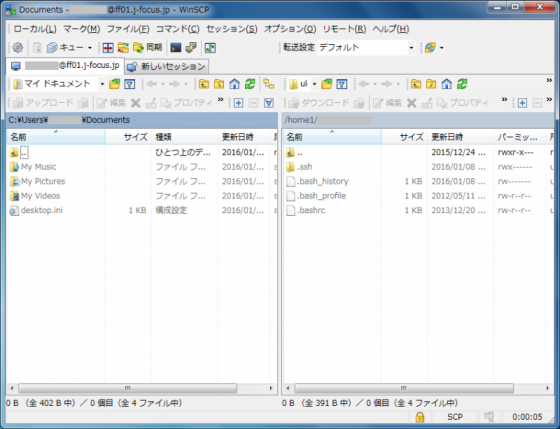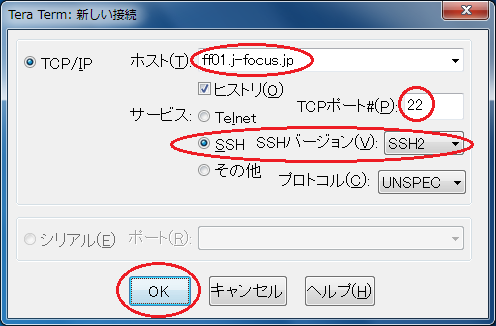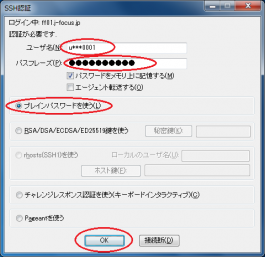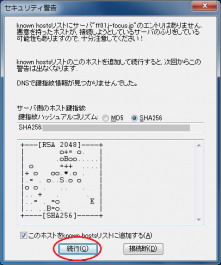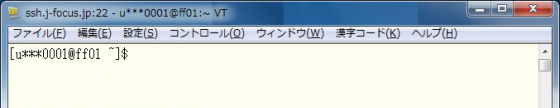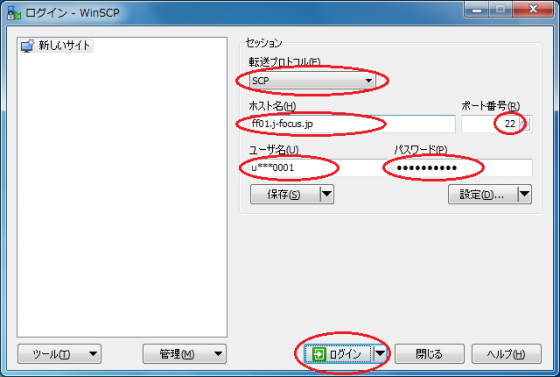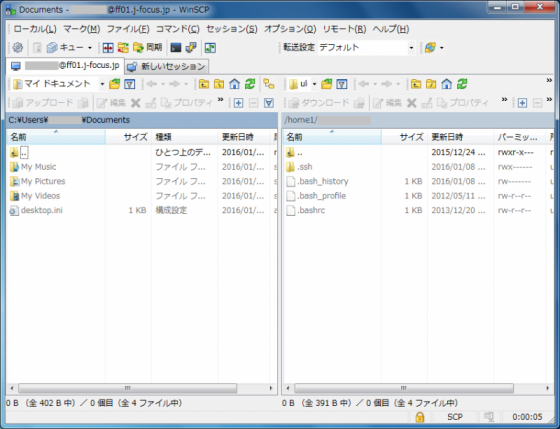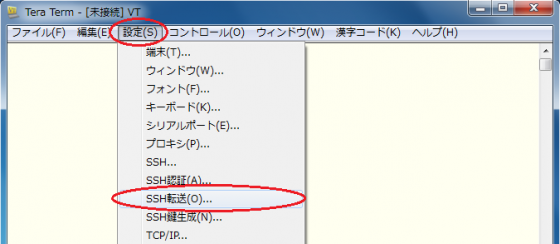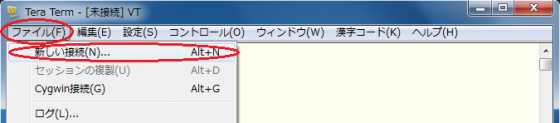目次 (2.1.システムへのログイン)
2.1. システムへのログイン
2.1.1. インターネットからのSSH接続によるログイン
2.1.1.1. 事前準備(秘密鍵・公開鍵の作成と登録)
2.1.1.2. ログインサーバへのSSH接続
2.1.1.3. 共用フロントエンドサーバへの接続
2.1.1.4. SCPファイル転送
①事前準備(秘密鍵の変換)
②SCPによるファイル転送(WinSCP使用)
2.1.1.5. X Window Systemを利用するアプリケーションの使用方法(Windows環境)
2.1.1.6. インターネットからのSSH多段接続によるログイン方法
・proxy設定によるSSH多段接続の設定方法
・Tera Termマクロ を使ったSSH多段接続の設定方法
・SCPによるファイル転送(インターネットからのSSH多段接続)
2.1.2. インターネットからのSSL-VPN接続による利用方法
2.1.2.1. SSL-VPN接続によるログイン
2.1.2.2. SSL-VPN接続によるSCPファイル転送(WinSCP使用)
2.1.2.3. X Window Systemを利用するアプリケーションの使用
2.1.3. 高度計算科学研究支援センター内でのログイン方法
▲このページの先頭へ
2.1.システムへのログイン
インターネットから、FOCUSスパコンシステムにログインするには、SSH鍵交換による接続法とSSL-VPNによる接続法の2経路があります。接続サーバ名等は、「付録A.FOCUSスパコンシステム各種サーバ・ストレージ概要」をご参照ください。
以下では、ログインの詳細な方法を記述します。
2.1.1.インターネットからのSSH接続によるログイン
お手元のマシンがインターネットに対してSSH接続できる環境であれば、SSH接続によりセンター内のシステムにアクセスすることができます。
以下の『2.1.1.1 事前準備(秘密鍵・公開鍵の作成と登録)』を実施して、公開鍵の登録が完了した後、ログインサーバ経由で共用フロントエンドサーバに接続できます。
図2.1.1 SSH接続イメージ
お手元のマシン
(localhost) |
→ インターネット → |
ログインサーバ
(ssh.j-focus.jp) |
→ |
共用フロントエンドサーバ
(ff.j-focus.jp) |
▲このページの先頭へ
2.1.1.1.事前準備(秘密鍵・公開鍵の作成と登録)
(1) スタートメニュー[すべてのプログラム]→[Tera Term]を順に選択します。
(2) Tera Term『新しい接続』画面で[キャンセル]ボタンをクリックします。
(『新しい接続』画面を閉じます。)
(3) Tera Termメニュー[設定]→[SSH鍵生成]を順に選択します。
(4)『TTSSH: 鍵生成』画面で、鍵の種類「RSA」(RSA2)を選択し、[生成]ボタンをクリックします。
(注)鍵の種類「RSA1、RSA、DSA」の中央に位置する“RSA”がRSA2です。
(5)「鍵のパスフレーズ」と「パスフレーズの確認」に同じフレーズを入力し、[公開鍵の保存]ボタンと[秘密鍵の保存]ボタンを押し、公開鍵と秘密鍵を保存します。
(6) OKBiz(https://secure.okbiz.okwave.jp/focus/)で公開鍵(id_rsa.pub)の登録を依頼します。
※ファイル名の初期値は次のとおりです。
・公開鍵:id_rsa.pub ←OKBizに添付するのは“.pub”の方です。
・秘密鍵:id_rsa ←お手元で管理してください(添付しないでください)。
※秘密鍵はSSH接続する際に使用します。
※秘密鍵はお手元で厳重に管理をお願いします(絶対に公開鍵と一緒に送付しないで下さい)。
※OKBizが使用不可の場合はメールで業務運用グループ unyo@j-focus.or.jpに送付してください。
▲このページの先頭へ
2.1.1.2.ログインサーバへのSSH接続
前述の手順『2.1.1.1. 事前準備(秘密鍵・公開鍵の作成と登録)』で作成した秘密鍵を使って、インターネットからログインサーバに対してSSH接続を行います。SSH接続に関わる各種情報は次のとおりです。
|
接続先 |
ssh.j-focus.jp |
|
サービス |
SSH |
|
ポート番号 |
22 |
|
サービスバージョン |
SSH2 |
|
認証方式 |
公開鍵認証 |
ご使用の環境によってはプロキシを設定する必要があります。そのような場合は、ご所属のネットワーク管理者にご確認ください。
手順は次のとおりです。
(1) スタートメニュー[すべてのプログラム]→[Tera Term]を選択します。
(2) TeraTerm『新しい接続』画面で以下の指定を行い、[OK]ボタンを押します。
|
・ホスト名 |
ssh.j-focus.jp |
|
・サービス |
SSH |
|
TCPポート# |
22 |
|
・SSHバージョン |
SSH2 |
(3) 『SSH認証』画面で以下の指定を行い、[OK]ボタンを押します。
なお、セキュリティ警告ウィンドウが現れた場合は、[続行]ボタンを押します。
|
・ユーザ名 |
センターから発行されたアカウント名(「u」+“課題名”+数字4桁) |
|
・パスフレーズ |
公開鍵・秘密鍵を作成した際に指定したパスフレーズ |
|
・RSA/DSA鍵を使う |
チェックを入れる |
|
・秘密鍵 |
お手元のマシンに保存している秘密鍵ファイル |
(4) プロンプト([アカウント名@login1~]$ もしくは[アカウント名@login2~]$)が表示されることを確認します。
▲このページの先頭へ
2.1.1.3.共用フロントエンドサーバへの接続
sshコマンドにより共用フロントエンドサーバff.j-focus.jp(ff)に接続します。
共用フロントエンド(ff01/ff02)上では、プログラムの開発、小規模な解析・デバッグ、
小規模なプリポスト処理の実行が許可されます。
ユーザーは下記の範囲での実行が可能です。
・CPU時間 1時間 (1時間で強制終了となります)
・プロセス数 1プロセス(並列実行、複数プロセスの起動は禁止です)
・利用メモリ 1GB程度 (小規模処理のみ許可)
上記範囲を越える場合は、バッチ処理より演算ノード上でジョブを実行してください。
または、専用フロントエンド(有償)の利用をご検討ください。
※専用フロントエンド上でのジョブ実行については、
実行時間、数、規模の制限はありません。(別途、申請書の提出が必要です)
【ffへの接続】
なお、初回接続時は確認メッセージが表示されるので、「yes」を入力します。
また、異なるアカウント名で接続する場合は、sshコマンドの -lオプションを使ってアカウント名を指定します。
【ffへの接続(アカウント指定あり)】
▲このページの先頭へ
2.1.1.4.SCPファイル転送
インターネットからログインサーバに対して、SCPファイル転送を行います。事前準備として秘密鍵の変換操作が必要となりますので、次の①、②の順で操作を行います。
①事前準備(秘密鍵の変換)・・・ PuTTY Key Generator(PuTTYgen)使用
②SCPファイル転送・・・ WinSCP
ホーム領域(/home1)は、ログインサーバと共用フロントエンドサーバが同じファイルシステムをマウントしているため、ファイルの転送操作はログインサーバに対してのみ実施します。
図2.1.1.4.1 ホーム領域(/home1)接続イメージ
お手元の
マシン
(localhost) |
→→
SCP |
インター
ネット |
→ |
ログインサーバ
(ssh.j-focus.jp) |
→ |
共用フロントエンド
サーバ
(ff.j-focus.jp) |
→→→→→
(マウント) |
ストレージ領域
/home1/グループ名
/home1/グループ名/アカウント名
/home1/グループ名/share |
→→→→→→→→→→→→→→→
(マウント) |
追加ストレージ領域(/home2)は、初期状態では共用フロントエンドサーバのみがマウントしています。ログインサーバからのマウントには、ユーザ単位での申請が必要となります。
図2.1.1.4.2 追加ストレージ領域(/home2)接続イメージ
お手元の
マシン
(localhost) |
→→
SCP |
インター
ネット |
→ |
ログインサーバ
(ssh.j-focus.jp) |
→ |
共用フロントエンド
サーバ
(ff.j-focus.jp) |
→→→→→
(マウント) |
ストレージ領域
/home2/グループ名(追加契約時) |
→→→→→→→→→→→→→→→
(マウントには申請が必要です)
|
なお、ご使用の環境によってはプロキシを設定する必要があります。そのような場合は、ご所属のネットワーク管理者にご確認ください。
①事前準備(秘密鍵の変換)
WinSCP用に秘密鍵をPuTTY形式に変換します。前述『2.1.1.1 事前準備(秘密鍵・公開鍵の作成と登録)』の手順で作成した秘密鍵(id_rsa)を使います。
(1) スタートメニュー[すべてのプログラム]→[WinSCP]→『ログイン - WinSCP』画面で[ツール]→[PuTTYgenを実行]を順に選択します。
(PuTTY Key Generatorを起動します。)
(2) PuTTY Key Generatorメニュー[Conversions]→[Import Key]を順に選択します。
(3)前述『2.1.1.1 事前準備(秘密鍵・公開鍵の作成と登録)』の手順で作成した秘密鍵を選択します。
※Windows環境の画面例
(4) 公開鍵・秘密鍵を作成した際のパスフレーズを入力し、[OK]ボタンをクリックします。
(5) [Save private key]ボタンをクリックします(変換した鍵が保存されます)。
▲このページの先頭へ
②SCPによるファイル転送(WinSCP使用)
前述の手順『①事前準備(秘密鍵の変換)』でPuTTY形式に変換した秘密鍵を使用します。
(1)スタートメニュー[すべてのプログラム]→[WinSCP]を順に選択します。
(2)『ログイン - WinSCP』画面で[設定]ボタンをクリックします。
(3)『高度なサイトの設定』画面で[SSH]→[認証]を順に選択し、以下の指定を行ないます。
|
・秘密鍵 |
PuTTY形式に変換した秘密鍵(∼.ppk) |
(4)『ログイン - WinSCP』画面に戻り以下の指定を行い、[ログイン]ボタンをクリックします。
|
・プロトコル |
SFTPまたはSCP |
|
・ホスト名/TD> |
ssh.j-focus.jp |
|
・ポート番号 |
22 |
|
・ユーザ名 |
アカウント名(「u」+“課題名”+数字4桁) |
|
・パスワード |
公開鍵・秘密鍵を作成した際のパスフレーズ |
(3) 『警告』画面が表示された場合は内容を確認し、[はい]ボタンをクリックします。
(4) 公開鍵・秘密鍵を作成した際のパスフレーズを入力し、[OK]ボタンをクリックします。
(5) 以下のような画面が表示され、お手元のマシンとログインサーバ間でファイル転送が出来るようになります。
▲このページの先頭へ
2.1.1.5.X Window Systemを利用するアプリケーションの使用方法(Windows環境)
(1) お手元のマシン(localhost)にCygwin/X 、Xming等のXサーバソフトウェアをあらかじめインストールしておき、お手元のマシン(localhost)でXサーバを起動します。
(2) スタートメニュー[すべてのプログラム]→[Tera Term]を順に選択します。
(3) Tera Term『新しい接続』画面で[キャンセル]ボタンをクリックします。(『新しい接続』画面を閉じます。)
(4) Tera Termメニュー[設定]→[SSH転送]を選択します。
(5) [リモートの(X)アプリケーションをローカルのXサーバに表示する]にチェックを入れ、[OK]をクリックします。
(6) Tera Termメニュー[ファイル]→[新しい接続]を順にクリックします。
(『新しい接続』画面を開きます。)
(7) ログインサーバにSSH接続します。(参照:『2.1.1.2 ログインサーバへのSSH接続』)
(8) ログインサーバから共用フロントエンドサーバ(ff01またはff02)にssh接続する際に、
-X (大文字エックス)オプションを付けます。
(9) 以上で、X Window Systemを利用するアプリケーションをお手元のマシンで利用出来るようになります。
▲このページの先頭へ
2.1.1.6.インターネットからのSSH多段接続によるログイン方法
前述2.1.1ではお手元のマシン(localhost)からログインサーバに接続し、そこから共用フロントエンドサーバに接続する方法を示しました。本節では、SSH多段接続によりlocalhostから直接フロントエンドサーバにログインする方法について示します。
・proxy設定によるSSH多段接続の設定方法
cygwin(Windows環境), MacOS X, Linux等のlocalhostで、$HOME/.ssh/config ファイルを以下のように設定します。ログインする共用フロントエンドサーバはff01.j-focus.jp、アカウント名はuser0001の場合の設定例になります。
【$HOME/.ssh/config 設定例】
Host FocusLogin #
HostName ssh.j-focus.jp # フロントエンドサーバの設定
User user0001 # アカウント名
Port 22 # ポート番号
IdentityFile ~/id_rsa # 秘密鍵の保管場所
Host ff01Focus
HostName ff01.j-focus.jp # ホストの指定
User user0001 #
ProxyCommand ssh FocusLogin nc %h %p #
|
configファイルでの設定終了後、フロントエンドへの接続を実行します。
【多段SSH接続実行例】
[localhost] $ ssh ff01Focus
Enter passphrase for key '~/id_rsa': ←公開鍵・秘密鍵のパスフレーズ
user0001@ff01's password: ←サーバログイン用のアカウントパスワードを入力
Last login: Wed Aug 29 14:05:10 2013 from login2.j-focus.jp
[user0001@ff01 ~]$ hostname
ff01.p
[user0001@ff01 ~]$
|
コマンドを使ってlocalhostから直接フロントエンドサーバへファイルのコピーを行うことも可能です。
【多段SSH接続を使ったscp実行例】
|
[local host] $ scp testfile ff01Focus:~ ←testfileをff01のホームにコピー Enter passphrase for key '~/id_rsa': ←公開鍵・秘密鍵のパスフレーズ user0001@ff01's password: ←サーバログイン用のアカウントパスワードを入力 testfile 100% 217 0.2KB/s 00:00 [localhost] $ |
▲このページの先頭へ
・Tera Termマクロ を使ったSSH多段接続の設定方法
Tera Term マクロを使い、ログインサーバへのSSH接続を自動化します。
(1) テキストエディタを使ってマクロを作成します。
以下では「FOCUS_FF.ttl」という名前でファイルを作成しています。
(接尾語は「.ttl」にしてください。)
LOGPATH = 'C:\<ログを保存したいパス>'
HOSTNAME1 = 'ssh.j-focus.jp'
HOSTNAME2 = 'ff.j-focus.jp'
USERNAME = 'アカウント名'
KEYFILE = 'C:\<事前準備で作成した秘密鍵の保管場所>\id_rsa'
COMMAND = HOSTNAME1
strconcat COMMAND ':22 /ssh /auth=publickey /user='
strconcat COMMAND USERNAME
strconcat COMMAND ' /keyfile='
strconcat COMMAND KEYFILE
strconcat COMMAND ' /ask4passwd'
connect COMMAND
LOGFILE = LOGPATH
strconcat LOGFILE HOSTNAME1
getdate datestr "%Y%m%d-%H%M%S"
strconcat LOGFILE '-'
strconcat LOGFILE datestr
strconcat LOGFILE '.log'
logopen LOGFILE 0 0 1 1 1
remote_prompt = '$'
wait remote_prompt
COMMAND = 'ssh '
strconcat COMMAND username
strconcat COMMAND '@'
strconcat COMMAND hostname2
sendln COMMAND
|
(2) エクスプローラを開き、該当ファイル(例「FOCUS_FF.ttl」)を右クリックし[プロパティ]を選択します。
(3)[ファイルの種類]→[変更]→[このファイルの種類を開くプログラムを選択]→[ttpmacro.exe]を選択します。
(4) 接尾語「.ttl」をもつファイル(例「FOCUS_FF.ttl」)をダブルクリックするとTera Termが起動します。
(5)「SSH認証」画面でパスワードを入力し、[OK]ボタンをクリックします。
(6) 以上の手順でフロントエンドサーバにログインできます。(「アカウント名@ff」コマンドは自動的に入力されます。)
▲このページの先頭へ
・SCPによるファイル転送(インターネットからのSSH多段接続)
ここでは前述の『2.1.1.4. SCPファイル転送』①事前準備で変換した秘密鍵を使用します。
(1) スタートメニュー[すべてのプログラム]→[WinSCP] を順に選択します。
(2)『ログイン - WinSCP』画面で「設定」ボタンをクリックします。
(3)[接続]→[トンネル]を順に選択し、以下の指定を行います。
|
・SSHトンネルを経由して接続 |
チェックを入れる |
|
・ホスト名 |
ssh.j-focus.jp |
|
・ポート番号 |
22 |
|
・ユーザ名 |
アカウント名(「u」+“課題名”+数字4桁) |
|
・秘密鍵 |
WinSCP用に変換したPuTTY形式の秘密鍵を指定
(鍵の変換方法は『2.1.1.4. SCPファイル転送』①事前準備を参照) |
(4) 「新しいサイト」を選択し、以下を指定し、[保存]ボタンをクリックします。
|
・ホスト名 |
ff01またはff02 |
|
・ユーザ名 |
アカウント名(「u」+“課題名”+数字4桁) |
(5) 『セッションの保存名』画面で保存名(例:FOCUSフロントエンド接続)を入力し、[OK]ボタンをクリックします。
(6) 『警告』画面(初回アクセス時のみ表示されます)が表示されたら、内容を確認したうえで、[はい]ボタンをクリックします。
(7) 『パスフレーズの入力』画面で公開鍵・秘密鍵のパスフレーズを入力し、[OK]ボタンをクリックします。
(8)アカウントのパスワードを入力します。
(9) 以上でお手元のマシン(localhost)とフロントエンドサーバ間でファイル転送が出来るようになります。
▲このページの先頭へ
2.1.2.インターネットからのSSL-VPN接続による利用方法
お手元のマシンがインターネットに対してSSL-VPN接続できる環境であれば、SSL-VPN接続でアクセスすることができます。また、ログインするときのホスト名、接続プロトコルは下表のとおりです。
|
システム名 |
ホスト名 |
接続プロトコル |
|
SSH |
telnet |
SCP |
FTP |
共用フロントエンドサーバ
(共用利用向け) |
ff01, ff02 |
○ |
× |
○ |
× |
専用フロントエンドサーバ
(占有利用向け) |
ft01, ・・・, ft04,
fm01, ・・・, fm08,
ff03, ff04 |
共用フロントエンドサーバの利用については 「2.1.1.3.共用フロントエンドサーバへの接続」に記載の 【共用フロントエンド利用についての注意点】をご確認ください。
▲このページの先頭へ
2.1.2.1.SSL-VPN接続によるログイン
SSL-VPN接続を使ってログインすることができます。
図2.1.2.1 SSH接続イメージ
お手元のマシン
(localhost) |
→ |
SSL-VPN接続
(インターネット) |
→ SSH接続 → |
共用フロントエンドサーバ
(ff01.j-focus.jp,ff02.j-focus.jp) |
手順は次のとおりです。
(1)SSL-VPN接続を開始します。接続方法は『SSL-VPN利用者マニュアル』(http://www.j-focus.jp/sslvpn/)を参照します。
(2)スタートメニュー[すべてのプログラム]→[Tera Term]→[Tera Term]を順に選択します。(Tera Termを起動します。)
(3)Tera Term『新しい接続』画面で以下を指定し、[OK]ボタンをクリックします。
|
・ホスト名 |
ff01.j-focus.jp または ff02.j-focus.jp
(混雑しないように ff01 と ff02 を使いわけてください。) |
|
・サービス |
SSH |
|
・SSHバージョン |
SSH2 |
(4)『SSH認証』画面で以下を指定し、[OK]ボタンをクリックします。
|
・ユーザ名 |
アカウント名(「u」+“課題名”+数字4桁) |
|
・パスフレーズ |
パスワード |
|
・プレインテキストを使う |
チェックする |
操作の途中で『セキュリティ警告』画面が表示された場合は[続行]ボタンをクリックして手順を続けます。
(5)以上の手順で共用フロントエンドサーバへのssh接続に成功すると、以下のような画面が表示されます。
▲このページの先頭へ
2.1.2.2.SSL-VPN接続によるSCPファイル転送(WinSCP使用)
SSL-VPN接続を使って、システムにSCPによるファイル転送を行います。
図2.1.2.2 SCPファイル転送
お手元のマシン
(localhost) |
→ |
SSL-VPN接続
(インターネット) |
→ SCPファイル転送 → |
共用フロントエンドサーバ
(ff01.j-focus.jp,ff02.j-focus.jp) |
手順は次のとおりです。
(1)SSL-VPN接続を開始します。接続方法は『SSL-VPN利用者マニュアル』(http://www.j-focus.jp/sslvpn/)を参照します。
(2)スタートメニュー[すべてのプログラム]→[WinSCP]→[WinSCP]を順に選択します。
(3)『WinSCPログイン』画面で以下の指定を行い、[ログイン]ボタンをクリックします。
|
・ファイルプロトコル |
SFTP |
|
・ホスト名 |
ff01.j-focus.jpまたはff02.j-focus.jp
(混雑しないように ff01 と ff02 を使いわけてください。) |
|
・ポート番号 |
22 |
|
・ユーザ名 |
アカウント名(「u」+“課題名”+数字4桁) |
|
・パスワード |
アカウントのパスワード |
(4) 下図のような画面でファイルを転送できるようになります。
▲このページの先頭へ
2.1.2.3.X Window Systemを利用するアプリケーションの使用
X Window Systemを利用するアプリケーションを使用する場合は事前に本手順を実行します。
(1)SSL-VPN接続を開始します。接続方法は『SSL-VPN利用者マニュアル』(http://www.j-focus.jp/sslvpn/)を参照します。
(2) スタートメニュー[すべてのプログラム]→[Cygwin-X]→[XWin Server]を順に選択します。
(3) スタートメニュー[すべてのプログラム]→[Tera Term]を順に選択します。
(4) Tera Term『新しい接続の設定』画面で、[キャンセル]ボタンをクリックします。
(5) Tera Termメニュー[設定]→[SSH転送]を順に選択します。
(6)『SSHポート転送』画面で、[リモートの(x)アプリケーションをローカルのXサーバに表示する]にチェックを入れ、[OK]ボタンをクリックします。
(7) Tera Termメニュー[ファイル]→[新しい接続]を順に選択します。
(8)前述の手順『2.1.1.2. ログインサーバへのSSH接続』、『2.1.1.3. 共用フロントエンドサーバへの接続』を使って、共用フロントエンドサーバにSSH接続を行い、続けてアプリケーション固有の操作を行うことで、X Window Systemを利用するアプリケーションを使用できます。
▲このページの先頭へ
2.1.3.高度計算科学研究支援センター内でのログイン方法
前述『2.1.2. インターネットからのSSL-VPN接続による利用方法』の各小節(2)以降の手順を使って、センター内からFOCUSスパコンシステムにログインできます。なお、講習用端末のハードディスクは、再起動すると初期化されますのでご注意ください。
▲このページの先頭へ